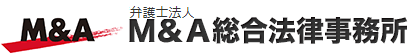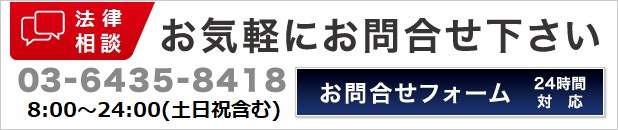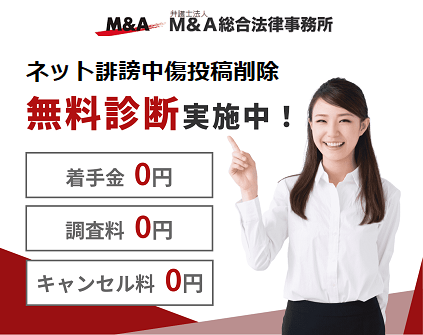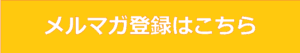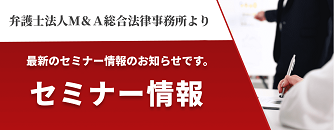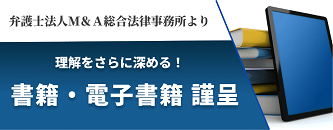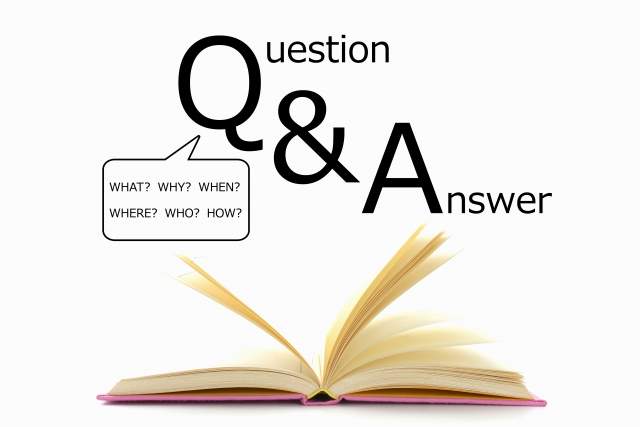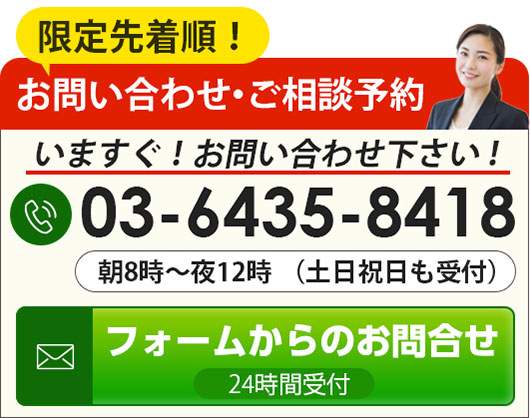SNSや個人ブログの急速な普及に伴い、匿名のネガティブな投稿に悩まされる企業が増えています。中には、事実とは異なる内容や、知的財産権の侵害にあたる内容のものも、数多く見られます。
自社に関する悪意の情報拡散に対しては、投稿主の氏名住所等を特定し、警告や損害賠償請求に着手するのが最も有効です。肝心の特定手段にあたるのが、本記事で紹介する「発信者情報開示請求」です。以降では、左記請求について一通り解説した上で、より難易度の低い削除請求の方法を紹介します。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、ネット上に流通する情報により権利侵害を受けた個人・法人・その他団体から、情報を扱うサイトの運営者等に対し、発信者の氏名住所等を開示するよう求める手続きです。本請求によって匿名性が失われれば、本人に投稿削除を求めつつ今後のネット上の発信について圧力をかけ、すでに被った実害については損害賠償責任や刑事責任を追及できます。
なお、開示請求の詳細な条件は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)で規定されています。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示請求の要件
発信者の氏名住所等の開示には、3つの要件があります。
各要件を満たすかどうかは、サイト運営者等が積極的に資料収集するわけではありません。法律をベースに「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成したガイドライン(リンク)を確認しながら、請求者自身で主張し、疎明※していく必要があります。
※疎明とは、ある事実について「確からしい」と証明できる程度の資料を提示することです。
権利侵害の明白性
発信者情報開示請求の第1の要件は、投稿内容による権利侵害が明白であることです。ここで言う権利侵害とは、個人に対する名誉毀損やプライバシー侵害、法人に対する信用毀損、著作権侵害、商標権侵害等を指します。
なお、権利侵害の明白性の判断については、下記のような着眼点があります。
【権利侵害の明白性を判断する要件】
- 客観的に見て、投稿内容からどんな内容や意味を読みとれるのか
- 名指しされた人物または団体の社会的信用を低下させていると言えるのか
- その投稿内容に違法性阻却事由(公共性・公益目的・真実性)はないか
- ③の要件について、投稿者が真実性を信じる相当の理由はないか
③・④に関しては、例として「コーポレートサイトに掲載されたIR情報に基づいて個人ブログ等に投稿されたケース」が考えられます。この例では、元々情報自体に公共性がある上、株主や一般消費者に対する公益目的、さらに真実性もあるため、発信者情報開示には応じてもらえません。
正当な理由の存在
開示請求の第2の要件は、正当な理由、つまり権利侵害に対して何らかの措置を講じる必要性があることです。例として、下記のようなものが挙げられます。
【例】発信者情報開示を受けるべき「正当な理由」とは
- 発信者に損害賠償請求したい。
- 発信者に投稿内容の削除を直接求める必要がある。
- 謝罪広告など、名誉回復措置を要請したい。
よくあるのは、既に権利侵害にあたる投稿が削除されているケースです。この場合、通常は「すでに請求の必要性がなくなっている」と判断できるため、発信者情報の開示は困難になります。
相手は特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者)か?
基本的な発信者情報開示請求の要件として、請求相手が「開示関係役務提供者」であることが、第3に挙げられます。
プロバイダ責任制限法第2条第1号では、上記通信は「特定電気通信」と呼称し、その媒介をする事業者を「特定電気通信役務提供者」と呼びます。この特定電気通信役務提供者こそ、他の請求要件を満たした時に、開示関係役務提供者となる立場です。
開示関係役務提供者となる請求の相手方としては、具体的に下記のようなものが挙げられます。
コンテンツプロバイダ
商品レビューやニュース等、情報発信サイトを運営・管理する事業者
(例)広告収益目的のサイトを運営する個人、営利目的のある法人、学校、その他団体など
ホスティングプロバイダ
個人や企業向けにサイトの公開スペースを提供する事業者。一般に「サーバ会社」とも
(例)webサイトの公開スペースを提供する会社、ドメイン取得代行業者
インターネットサービスプロバイダ(ISP)
自社の基地局等にアクセスする利用者に対し、インターネットへの接続を媒介し、メールアドレスの付与なども行う事業者
(例)発信者が投稿するために利用したインターネット会社、携帯電話会社など
※携帯電話は回線事業とISPが一体化している事業者です。
発信者情報の保有
忘れられやすい第4の要件は、開示請求先であるプロバイダが「発信者情報を保有している」ことです。
請求手続きでは、発信者情報について「わざわざ指摘するまでもなく当然保有している」との前提で始められがちです。しかしこれでは、相手となるサイト運営者等から、実際の保有有無に関わらず「すでにアクセスログが消えていて対応できない」等と主張されてしまいます。この点、相手の情報保有をしっかり指摘するよう、請求書類の作成で注意しなければなりません。
ネット誹謗中傷に関連して開示される発信者情報の種類
ネット上の風評被害にさらされた企業として気になるのは、開示請求できる発信者情報の内容です。この点、プロバイダ責任制限法第4条第1項では、氏名・住所を含めて下記8点が挙げられています。
【開示できる発信者情報の種類】
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- IPアドレス・ポート番号
- インターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- タイムスタンプ
実際の開示請求では、1度の手続きで上記①~③の情報(=発信者の身元を特定できるもの)が得られるケースは稀です。そこで、以降解説するように、手続きを2段階に分けて個人情報の特定を目指すのが一般的です。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示請求の手順
発信者情報開示請求の第1段階は、サイトの管理・運営・データ保管等を行う事業者に対する請求です。つまり、コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダが請求の相手方となります。実名サイトであれば、上記事業者が「氏名住所等の発信者の特定にいたる情報」を保有しているため、この段階で発信者特定に至れます
しかし、実際の請求例では、ほとんどの場合が匿名サイトです。この場合、サイト運営者等は氏名住所等の情報を保有しておらず、開示には至りません。そこで第2段階として、投稿の際に経由したプロバイダ、つまりネット利用のため契約している携帯電話会社等への開示請求が必要になります。
【発信者情報開示請求の大まかな手順】
実名サイト:サイト運営者(管理者)に対する請求のみ
匿名サイト:サイト運営者(管理者)に対する請求+経由プロバイダへの請求
以下では、匿名サイトでの開示請求を前提に、発信者の身元を特定するまでの手続きを4ステップに分けて紹介します。
サイト運営者・サーバ―会社等の特定
問題の投稿先が大手サイトなら、一見して運営・管理元の事業者名が分かるため、本プロセスは無視しても構いません。しかし、個人ブログ、いわゆる「まとめサイト」、その他の小規模な匿名掲示板等では、運営・管理の主体が明確でないものが多く見られます。
上記のようなサイトに関しては、下記のような解析ツール(通称“Whois検索”)にURLを入力し、コンテンツプロバイダあるいはサーバ会社等を特定します。
IPアドレスの特定
サイト運営者等の特定に至れば、発信者情報開示請求の第1段階を開始します。ここでは、投稿日時の記録である「タイムスタンプ」や、発信者特定を進める上で欠かせない「IPアドレス」を得ることが目的です。
注意したいのは、請求手続きは一般社団法人テレコムサービス指定の書式(テレサ書式)の使用が必須である点です。それ以外の方法(問い合わせフォームからの依頼等)では情報開示に応じてもらえません。
意見照会書とは?
なお、発信者情報開示請求書が送達されると、相手方であるサイト運営者等から問題の発信者に対して「意見照会書」が送付されます。
本照会書は、開示請求に同意するか否かの回答を得るためのものですが、同意がないからといって情報が開示されないわけではありません。開示拒否あるいは2週間以内に回答がなかった場合でも、請求書に添付した資料から「要件を満たしている」とサイト運営者等が判断すれば、情報開示に至ります。
任意開示手続きに応じない場合の対応
サイトの管理・運営を行う事業者によっては、例えば「表現の自由」などを盾に任意開示手続きに応じないケースもあります。この場合、代理人による弁護士法第23条の2に基づく照会とするか、裁判手続に切り替える他ありません。
経由プロバイダの特定
コンテンツプロバイダ等からの開示情報には、発信者を識別するためのIPアドレスがあります。請求の第2段階目に移るには、上記アドレスを使って経由プロバイダを特定しなければなりません。ここで言う経由プロバイダとは、投稿時に発信者のインターネット接続を媒介したISPを指します。
本特定でも、サイト運営者・サーバ―会社等の特定で利用できるWhois検索ツールを使用します。
発信者情報の特定
発信者情報開示手続きの第2段階である経由プロバイダへの請求でも、同じくテレサ書式で開示請求を行います。
と言っても、コンテンツプロバイダ等に対するものとは異なり、ISPへの任意開示手続きはほとんど成功しません。警察やその他行政庁からの照会でないと対応できない、調査に時間がかかる、等の理由で開示を渋られるため、大半のケースで後述の「発信者情報開示請求訴訟」を提起します。
発信者が格安携帯を使用している場合の対応
発信者が格安携帯を使用する場合、MVNO(仮想移動体通信事業者)に辿りつくまで発信者情報開示請求を繰り返さなければなりません。
ステップ2の時点で特定できるのは、自社の回線を格安SIMカード提供会社等に貸し出すMNO(移動体通信事業者)です。そして、MNOは格安携帯利用者の氏名情報を持っていません。顧客情報を持っているのは、借りた回線で利用者を募る会社、つまり格安SIMカード会社等にあたるMVNOです。
中には、MVNOではなく、その契約締結や通信機能を支援する別の会社が顧客情報を保有する運営形態もあります。そのため、3回~4回ほど開示請求を繰り返さなければ発信者の特定に至らないケースが見られます。
【例】格安携帯を利用する発信者への対応
MNOへの開示請求
…NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天のいずれか
▼
MVNOへの開示請求
…LINEモバイル等
▼
MVNEへの開示請求
…NTTコミュニケーションズ、ソニーネットワークコミュニケーションズ等
意見照会で発信者にプレッシャーを与えられる
いずれ裁判手続に移行するからと言って、任意開示手続きにまったく意味がないわけではありません。先述の意見照会書が警告文としての機能を果たし、発信者に対して迅速に「これ以上風評被害にあたる投稿を繰り返してはならない」とのプレッシャーを与えられるからです。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示のためアクセス記録保全の重要性
プロバイダで管理する発信者のアクセス記録は、日本法人なら3か月程度、海外法人なら2週間程度で消去されます。対処のスピード感は言うまでもなく重要ですが、請求手続きに時間がかかってしまう場合は、アクセス記録の消去を禁じるための裁判手続として「発信者情報消去禁止の仮処分命令」を申立てなくてはなりません。
この際、仮処分命令の前提となる「被保全権利」は発信者情報開示請求権となります。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示請求訴訟の流れ
ISPやコンテンツプロバイダ等を相手に行う「発信者情報開示請求訴訟」は、一般に下記の流れで進みます。本手続きは通常3か月~6か月、ケースによっては1年以上の長期戦です。
管轄裁判所の確認
はじめに確認しなければならないのは、管轄の裁判所です。ポイントは、相手が日本法人か海外法人かで管轄が異なる点です。
日本法人の場合
…住所、または主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所へ訴えを提起します。(民訴法4条第1項・4項)
海外法人の場合(Twitter・Google・Facebook等)
日本において事業を行う者に関しては、日本の裁判所が管轄です(民訴法第3条3の第5号)。併せて、東京都千代田区所轄の裁判所が管轄とされているため(民訴訟第10条2・規則6条2)、結論として東京地方裁判所が管轄となります。
訴訟提起
訴訟提起時、請求の趣旨として「どんな情報を開示してほしいのか」具体化する必要があります。ここでは、特段の事情がない限り、下記3点の開示を被告に求めます。
【請求の趣旨】
- 氏名または名称
- 住所
- 電子メールアドレス
口頭弁論期日
期日においては、権利侵害の明白性等の発信者情報開示請求における要件を主張し、正当な請求であることを説明します。風評被害に遭った企業の主張に正当性があれば、一般的には3回程度の期日で結審します。
なお、発信者がプレッシャーに屈して開示に同意した場合は、結審・判決を待たずに速やかに開示されます。
判決
勝訴判決が下れば、控訴されることはほとんどありません。
この時点で発信者情報の開示が行われ、損害賠償請求や本人に対する削除請求、その他刑事告訴等に移行できます。
ネット誹謗中傷の発信者情報開示請求の訴訟費用
発信者情報開示請求にかかる訴訟費用の目安は、実費のみで最大10万円程度です。
なお、前述の「発信者情報消去禁止の仮処分命令」には、相手方が受ける損害に配慮し、下記のように担保金を供託する必要があります。上記実費の大半を占めるのは、この仮処分命令にかかる担保金です。
【訴訟費用(実費)の内訳】
手数料:13,000円※
送達用の切手代:1,000円~1,500円(裁判所による)
仮処分命令にかかる担保金:10万円程度
※手数料は訴訟の目的価額に応じて定められています。発信者情報開示請求では「算定が極めて困難」として、目的価額=160万円とみなされ、対応する金額を支払うのが一般的です。
ネット誹謗中傷投稿記事の削除請求
企業として最も気がかりなのは、風評被害の元となった記事をネット利用者の目に触れさせないように出来るかどうかでしょう。
削除請求の手続きの大まかな流れとしては、まず削除を実行できる事業者等を特定し、任意請求もしくは裁判手続を実施します。削除請求のポイントや具体的な方法については、以降で解説する通りです。
まずは証拠を保全する
後々発信者本人に責任を追及する際、先に削除されてしまっては、肝心の立証手段を得られなくなってしまいます。そこでまずやっておきたいのは、風評被害等に関する証拠保全です。
具体的には、投稿内容をパソコンやスマートフォンに表示させてスクリーンショットを取る、あるいはプリントアウトする等の方法が挙げられます。
削除請求の方法
証拠保全が済めば、削除請求の方法を検討します。風評被害にあたる情報を素早く削除してもらうには、下記3点のうち、投稿先サイトの性質に遭うものを選択しなければなりません。
問い合わせフォームから削除請求する
投稿内容の違法性が明確である場合、即日~2週間以内の削除が期待できます。ただし、個人が管理するサイトや、対応速度の遅い企業が運営するサイトについては、スムーズな対応は期待できません。
ガイドラインに沿って削除請求の依頼書を送付する
発信者情報開示請求と同じく、所定のテレサ書式で削除依頼を行う方法です。発信者への意見照会が行われる点も同様で、削除拒否された場合、請求相手となるサイト運営者の判断(客観的に見て権利侵害が明白かどうか)に委ねられます。
なお、発信者からの回答が7日以内になかった時は、権利侵害の明白性の有無に関わらず、依頼主の希望通り投稿削除が行われます。
法的手段で削除を実施させる
サイト運営者等が削除に応じない、あるいは発信者本人に削除を求めるしかない場合は、裁判手続を検討する他ありません。具体的には、投稿記事等削除の仮処分命令を申し立て(民事保全法23条2項)、削除するまで命じられた金額を支払わなければならない(民事保全法52条1項・民事執行法172条)とプレッシャーを与える方法です。
上記の申立では、命令が発せられるまで1か月~2か月かかる他、30万円程度を目安に担保金の供託が発生します。供託した金銭は担保取消決定等の一定の手続きで返却されますが、削除まで時間がかかる点はネックです。
代理弁護士が内容証明郵便を送付するだけで削除実施に至るケースもあるため、試す価値は十分あるでしょう。
削除代行業者の危険性
ネット上のネガティブな投稿が急速に増加する影響で、削除請求を代行する業者が多数現れています。こうした業者による請求は、どのような方法であれ弁護士法違反です(東京地判平成29年2月20日)。
このような業者を利用した場合、削除請求の相手方がいわゆる「炎上」に持ち込む等して、かえって企業イメージが低下します。また、そもそも適正な手続きが実施されるとも限りません。弁護士でない「削除代行業者」と名乗る人物には、絶対に依頼しないようにしましょう。
検索サイトに対しても削除請求を行う
誹謗中傷等にあたる記事の削除に成功しても、Google等の検索サイトには履歴が残ってしまいます。そこで、上記サイトに対して古いコンテンツを削除するよう依頼することも、風評被害・営業妨害を抑止するため欠かせないフローです。
ネット誹謗中傷の発信者への損害賠償請求
特定した発信者に慰謝料を支払わせたい時は、内容証明郵便の送付、もしくは損害賠償請求訴訟を行います。
以降では、支払わせられる金額の目安、内部関係者による行為だった時の対応方法、さらに刑事責任について解説します。
損害賠償額の相場
過去の判例等によれば、損害賠償額の相場は30万円~60万円程度です。
発信者特定までにかかった費用に関しても、相手に請求できる可能性があります(東京地判平成24年1月31日・東京高判平成24年6月28日)。
発信者が従業員だった場合の対応方法
発信者が従業員だった場合は、損害賠償請求とは別に懲戒処分も検討しなくてはなりません。通常、職場外の行為に関しては処分の対象にならないものの、従業員の忠実義務に含まれる「会社の信用や名誉を毀損しない義務」や「秘密保持義務」に違反するものとして処分できる可能性があります。
刑事責任の追及について
特に悪質なケースでは、刑事告訴を検討することも可能です。当てはまる犯罪の例としては、下記のいずれかが考えられます。
侮辱罪(刑法第231条)
→拘留または過料
名誉毀損罪(刑法第230条第1項)
→3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
威力業務妨害罪(刑法第234条・第233条)
→3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
まとめ
発信者の特定にかかる情報開示請求権は、プロバイダ責任制限法で認められています。
その行使にあたっては、問題の投稿について記録を保有する事業者全てに対し、任意もしくは裁判上の手続きを経なければなりません。各事業者の特定にあたっては、IT技術への一定の理解が必須です。また、アクセスログが一定期間経てば消去されることを考慮すれば、対処にはスピードが要求されます。
対処スピードについては、記事等の削除請求の方がより求められるでしょう。ネット上に恣意的な風評が掲載される期間が長引くほど、売上低下・信用毀損・人材確保の難易度上昇等の被害が拡大するからです。
これらの対応を社内だけで実施しようとすると、知識不足が仇となって後手に回りがちです。万一の際は早急に弁護士に相談し、対応を検討してもらうようにしましょう。